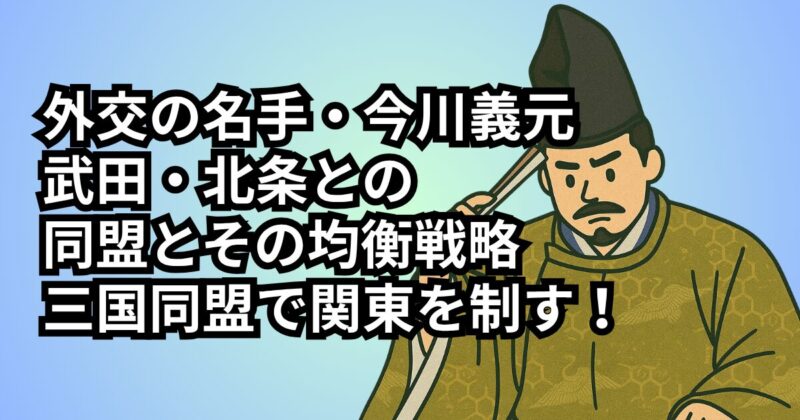はじめに|「外交巧者」としての今川義元を再評価しよう
「桶狭間の敗者」として語られがちな今川義元。しかし、彼の本質を知れば知るほど、優れた戦略眼を持った“バランス外交の名手”であったことが浮かび上がります。
今回は、今川義元が築いた甲相駿三国同盟(武田信玄・北条氏康との三国間協調体制)に注目し、その狙い・仕組み・維持努力、そして現代ビジネスにも通じる外交・交渉術を解説していきます。

甲相駿三国同盟とは?|戦国時代における「バランス・オブ・パワー」
🏔 同盟の概要
「甲相駿三国同盟(こうそうすんさんごくどうめい)」とは、甲斐の武田信玄、相模の北条氏康、駿河の今川義元という三者が手を結んだ軍事・政治同盟です。
- 甲=甲斐(武田家)
- 相=相模(北条家)
- 駿=駿河(今川家)
これは、戦国時代では異例ともいえる**「周囲との勢力均衡を維持しつつ、領土拡大を目指す」**高度な外交戦略の一環でした。
🕊 同盟の背景
当時、信濃・上野・関東では上杉謙信(長尾景虎)が勢力を伸ばしており、北関東に対する牽制が必要でした。一方で、今川家は西の織田家、東の北条家との板挟み状態。三国同盟は、これらの地政学的リスクを抑えるための「防衛的布陣」でもあったのです。
今川義元の外交力が光った3つのポイント
1|敵対していた北条氏との和睦と縁組
今川家と北条家は、元々は敵対関係にありました。天文14年(1545年)の「河東の乱」では、両家が駿河・相模の国境を巡って争っていたのです。
しかし義元は、敵対関係をあえて「共通の敵(上杉・織田)に備えるための協調関係」に変える戦略を取りました。決定打となったのが、自らの妹を北条氏康に嫁がせる政略結婚でした。
→ 政略結婚=戦国時代の同盟構築における「人的ネットワークの固定化」
これは現代でいえば、敵対的関係にあった企業同士が「資本業務提携」や「合弁会社設立」で利害調整を図るようなものです。
2|信玄との婚姻と信濃への睨み
さらに義元は、武田信玄とも強固な関係を築くため、自らの娘(あるいは養女)を信玄に嫁がせました。
これにより、信玄の信濃侵攻に対して今川が後方支援を担う構図ができ、同盟関係が一層強固になりました。
→ 甲斐=内陸部の武力、駿河=経済力と海路、相模=外交・情報。三者三様の強みが融合する協調体制が実現しました。
3|バランスのとれた三角関係を維持する調整術
三国同盟は一時的な同盟ではなく、十数年以上にわたって機能しました。
これは、単に「仲良し」だから続いたのではなく、利害関係が明確で、かつ“絶妙な距離感”があったからです。
- 直接的な利害対立を避ける境界調整
- 軍事行動に関する情報共有の徹底
- 経済的な利得(物流・塩・商業)による相互依存
→ まさに現代の国際関係における「アライメント(同盟)」の先駆けでした。
なぜこの同盟は破綻したのか? 義元の死と信玄の駿河侵攻
永禄3年(1560年)、今川義元が桶狭間の戦いで戦死すると、この同盟関係は次第に綻びを見せます。
武田信玄の駿河侵攻(永禄11年)
義元の死後、武田信玄は同盟を破棄し、駿河へ侵攻を開始します。これは義元の後継者・今川氏真の統治能力不足や、外交の軸が失われたことによるものでした。
→ 義元という“同盟の調整役”がいなくなったことで、力の均衡が崩れたのです。
ここからは三国間の協調が消え、戦国の嵐が再び吹き荒れることになります。

現代ビジネスに生かす「今川式バランス外交」の教訓
🧭 リーダーの「調整力」が組織を保つ
今川義元の外交で最も学ぶべきは、「調整力」と「共通の利害による連携」です。
- ライバル同士を利害で結ぶ
- 信頼よりも依存構造を重視する
- “直接対立を避ける距離感”を維持する
これは企業間の提携や社内の部門間調整にも応用できます。
💡 組織における「多角的パートナー戦略」
義元のように、一方向に依存せず、複数のパートナーと協調する戦略は、VUCA時代の企業経営にとっても重要です。
「信頼と緊張」「自立と依存」の絶妙なバランスを取る──それこそが、戦国と現代をつなぐ“生き残りの戦略”ではないでしょうか。
まとめ|らぼのすけ的「戦わずして守る」外交術
ぼく「らぼのすけ」は、今川義元の外交から「戦わずに国を守る」という戦略の奥深さを学びました。
・敵を味方に変える柔軟さ
・交渉の中で“共通の敵”を探す知恵
・相手との“ちょうどいい距離”を保つバランス感覚
これらの力は、どんな時代にも求められる「戦わずに勝つ」ための知略なのかもしれません。
次回は第5回:「義元軍の再評価と『海道一の弓取り』の真価」──義元の軍事面に焦点を当てて、実際の戦力や兵の構成についても詳しく掘り下げていきたいと思います!
それでは、また次の“戦国知恵袋”でお会いしましょう!