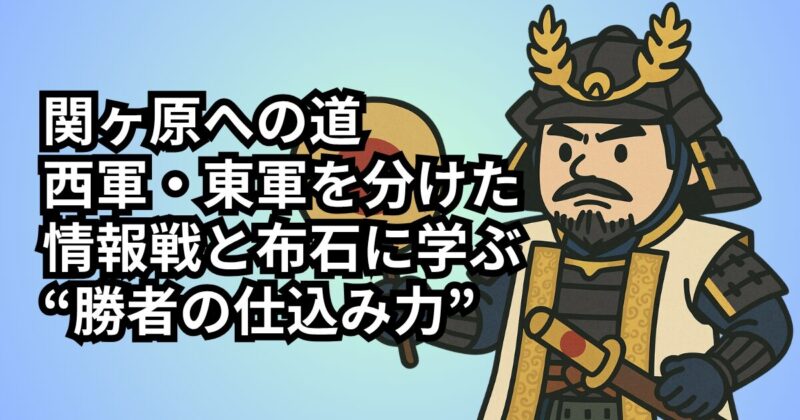はじめに:関ヶ原は「突然の戦い」ではなかった
1600年、徳川家康と石田三成が激突した「関ヶ原の戦い」。日本史でも屈指の決戦として知られていますが、実はこの戦いは突発的に始まったわけではありません。
家康は関ヶ原の約1年前から、水面下で緻密な情報戦と布石を打ち続けていました。今回は、「なぜ家康は勝てたのか?」という問いに対し、戦いの“前段階”に焦点を当てて読み解いていきます。

1. 秀吉の死と「五大老体制」の崩壊
豊臣政権の設計:五大老と五奉行
豊臣秀吉の晩年、日本の統治を安定させるために考案されたのが「五大老・五奉行体制」でした。これは、有力大名(徳川家康・前田利家・毛利輝元・小早川隆景(死後は上杉景勝)・宇喜多秀家)を「大老」とし、行政を実務的に担う「奉行」(浅野長政・石田三成・増田長盛・長束正家・前田玄以)とで権力を分担する体制です。
しかし、秀吉が1598年に亡くなると、体制は一気に不安定化。幼少の秀頼では、重臣たちの権力闘争を抑えることができませんでした。
2. 家康の静かな台頭と「三成包囲網」
家康は「秀吉の遺児・秀頼を支える立場」でありながら、徐々に権力を掌握していきます。
・諸大名との縁組政策(政略結婚)
・江戸を拠点にした軍備増強
・奉行衆への影響力拡大
これに対して強く反発したのが石田三成でした。三成は、家康の行動を「豊臣家への裏切り」と捉え、大谷吉継・宇喜多秀家らと密かに「家康追討」の動きを進めていきます。
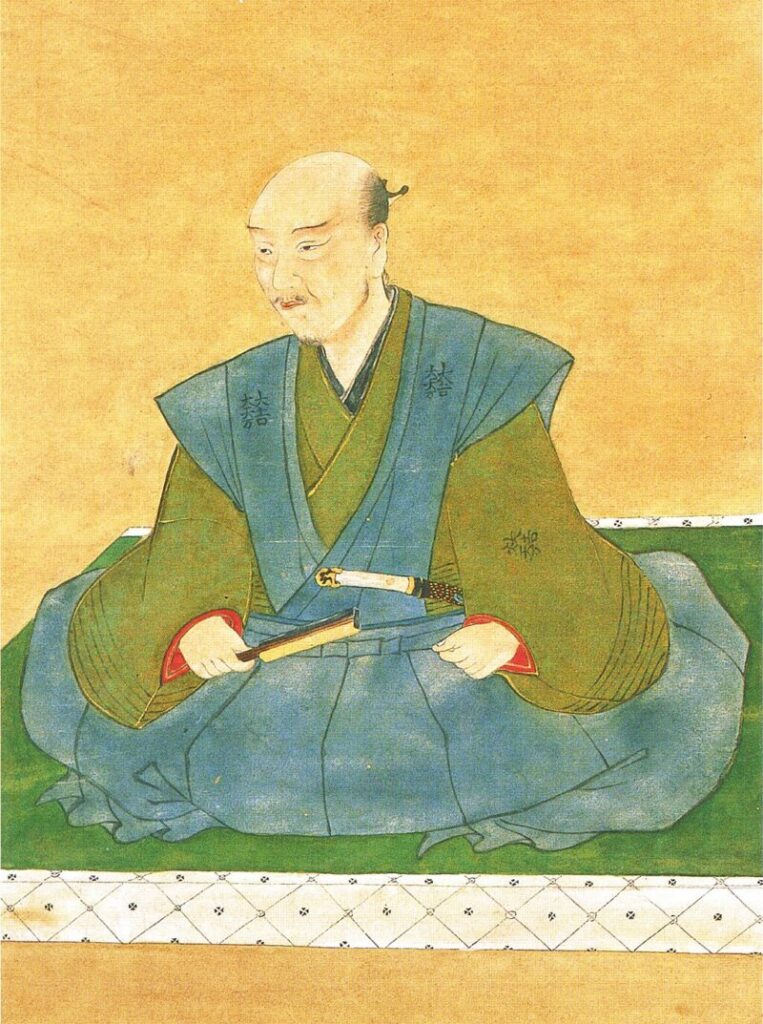
3. 家康の先手:「上杉討伐」を口実に西の敵を炙り出す
上杉景勝の動きと「会津征伐」
1600年、上杉家が「無断で城の増築・兵の動員」を行っているという報が江戸に届きます。これを口実に、家康は諸大名を従えて「会津征伐」に向かいます。ここで重要なのは、家康があえて江戸を離れたこと。
この“隙”を突いて、三成らは「家康追討」の挙兵に踏み切ります。つまり、家康にとっては上杉討伐は「敵をあぶり出すための罠」だったともいえるのです。

4. 家康の情報戦略:「西軍内の分断工作」
三成率いる西軍のほうが、兵力では優位とされていました。しかし家康は、そこに潜む“弱点”を見逃しませんでした。
西軍の構造的問題
- 名目上の総大将は毛利輝元(しかし動かない)
- 内部には「三成嫌い」の武将が多数
- 地理的に東西連携がとりづらい
家康はこれらを逆手にとって、以下のような「分断工作」を展開しました。
- 小早川秀秋への調略(裏切りの誘発)
- 毛利本家への密書送付(中立化を狙う)
- 島津義弘にはあえて干渉せず、傍観させる
これらの工作は、戦う前から勝利の布石として極めて大きな役割を果たしました。
5. 「東軍結集」と家康のリーダーシップ
西軍の挙兵を聞いた家康は、即座に会津征伐を中止し、Uターンで西へ向かいます。この際の判断と行動の速さが、関ヶ原の勝敗を左右しました。
また、東軍に味方した諸将の心理にも注目です。
- 福島正則や加藤清正など、もともと豊臣恩顧の大名
- それでも家康に与したのは「三成ではなく家康に天下を託したい」という判断
ここには、家康の“信頼資産”がすでに出来上がっていたことが伺えます。
6. 決戦前夜:関ヶ原の地に布かれた盤面
関ヶ原の戦場選びにも、家康のしたたかな戦略が見えます。
・西軍の主力を西美濃に引き込む
・関ヶ原の地形(湿地帯と山間)を活用
・裏切りを確実に見届けられる視界設計
つまり、ただ戦うのではなく「勝ちやすい場所で戦う」ための環境整備がなされていたのです。

7. ビジネスに活かす関ヶ原前夜の家康流“仕込み力”
現代においても、家康の動きから学べる点は多くあります。
【1】外見上の「ルール遵守」を貫く
家康は最後まで「豊臣政権の守護者」の姿勢を崩しませんでした。公然と反旗を翻すことはせず、敵の不正を理由に動く。その姿勢が、味方を得る信頼につながります。
▶️ 現代応用:正論の装いを保ちつつ、内部で主導権を握る
【2】敵の分断を狙う心理戦術
家康は武力ではなく、心理と情報で勝ちを呼び込みました。人間関係や内部矛盾を見抜いて、あえて「何もしない」ことすら選択肢に加えています。
▶️ 現代応用:競合企業の弱みは、正面衝突せずとも分断で攻略可能
【3】勝てる“盤面”を整えてから動く
関ヶ原という地の選定、調略の完了、東軍の結集。家康はあらゆる要素が整うまで、決戦を起こしませんでした。
▶️ 現代応用:勝負に出る前に、下準備・情報収集・信頼構築を徹底する
まとめ:関ヶ原は「勝てるように設計された戦」
表面的には「東軍 vs 西軍の戦い」ですが、真の勝負はその前から始まっていました。
徳川家康が勝ったのは偶然ではありません。綿密な情報戦、地ならし、心理戦を経て、戦わずして勝つ仕組みを構築していたのです。
「勝てる戦しか、しない。」
これは家康が実践した現代でも通じる“経営哲学”ではないでしょうか。
この続きとなる第7回では、「関ヶ原後の徳川家康と“江戸幕府への道”」をテーマに、天下統一の最終段階を紐解いていきます。
ご期待ください。