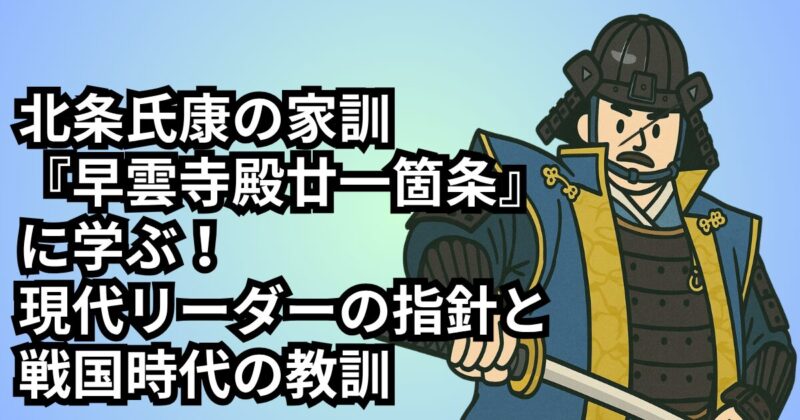はじめに|“家訓”とは何か? その意義を改めて考える

戦国時代、混乱の世を生き抜くために、武将たちは自らの家や組織をまとめる“指針”を残しました。それが「家訓」です。
家訓は単なる規則集ではなく、その家の「心の軸」となる考え方や、日々の行動のあり方を示すものでした。
現代でいえば、会社の「経営理念」や「クレド(行動規範)」に近い存在かもしれません。
特にリーダーや組織のトップが、その家訓をどのように考え、活かしていたかは、現代のビジネスリーダーにも多くのヒントを与えてくれます。
今回は、戦国大名・北条氏康の家訓「早雲寺殿廿一箇条(そううんじどのにじゅういっかじょう)」を題材に、リーダーの心構えを考えてみましょう。
北条氏康の家訓「早雲寺殿廿一箇条」とは?
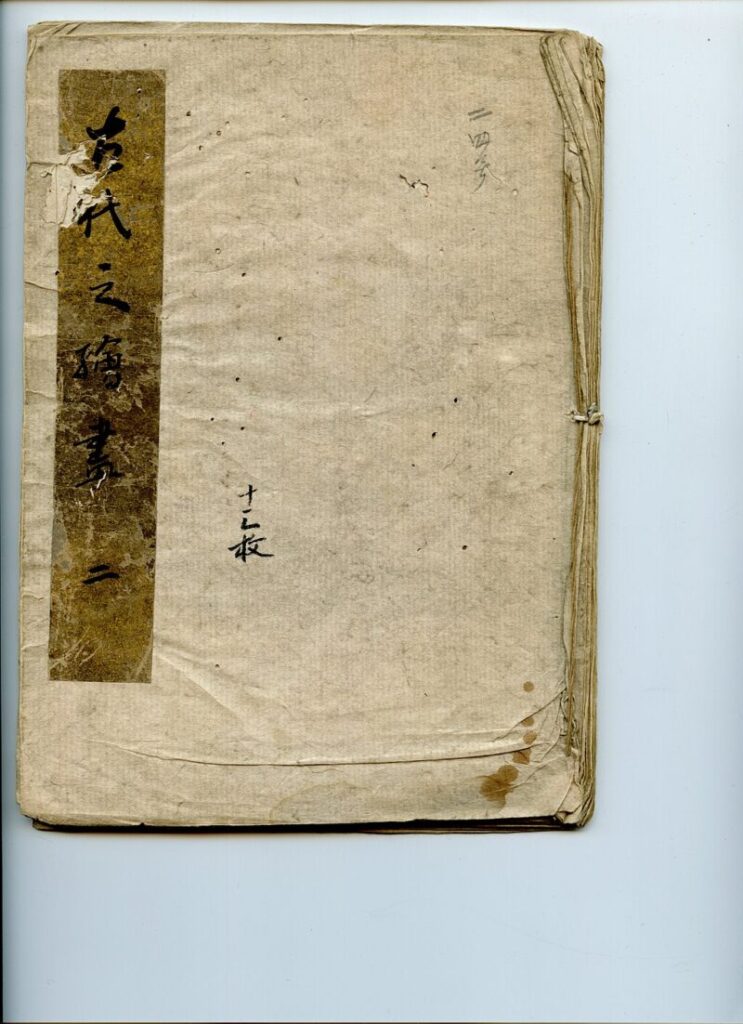
北条氏康は、相模国の戦国大名として知られています。彼が残したとされる家訓『早雲寺殿廿一箇条』は、家臣や子孫に向けた具体的な行動指針の集大成です。
この家訓は、父・北条氏綱の教えを受け継ぎながら、氏康自身の政治哲学が色濃く反映されています。
全21条の内容は、どれも「礼節」「公正」「倹約」「忠誠」といった普遍的な価値観に貫かれており、時代を超えて心に響く教えが並んでいます。
当時の戦国時代には、国を支えるルールや法律が整っていない部分も多くありました。そんな中で、リーダーが自らの家訓として価値観を明文化し、家臣や家族に伝えることは、組織の安定を守るために重要だったのです。
家訓は「思考の型」を渡すもの

家訓の最大の役割は、日々の判断基準を家臣や後継者に示すことにあります。
氏康の家訓には、以下のような言葉が含まれています。
- 人に対しては常に礼を尽くすこと
- 欲に走らず、私利私欲を避けること
- 言葉遣いを慎み、敵味方を問わず丁寧に接すること
これらは一見、当たり前のように思えるかもしれません。
しかし、戦国時代という常に生死がかかる世界において、こうした姿勢を貫くのは容易ではありませんでした。
だからこそ、家訓として残し、代々の心の支柱として伝えたのです。
また、家訓は抽象度が高く、場面によって柔軟に応用できるように書かれていることが多いです。
まさに「思考の型」として、どんな時代にも通じる普遍性を意識していたのです。
礼節と公正を重んじる氏康のリーダーシップ
氏康の家訓には、相手を尊重し、公正であろうとする姿勢が随所に見られます。
たとえば「敵味方を問わず礼を尽くす」という教え。戦場の敵であっても、敬意をもって接することの大切さを説いています。
これは現代に置き換えると、競合他社や異なる立場の相手でも、基本的な礼儀や公正さを忘れないことの重要性に通じます。
数字や成果ばかりに目が向きがちな時代だからこそ、こうした価値観がますます必要とされるのではないでしょうか。
氏康の「民を思いやる政治」から学ぶ

もうひとつ、氏康の家訓や政治姿勢の特徴として「民を思いやる」視点があります。
彼は災害が起きれば年貢を免除し、農民が立ち直るまで支援を惜しまなかったという記録があります。
これは単なる施しではなく、「民の生活が安定すれば、国全体が強くなる」という確信に基づくものでした。
現代のビジネスに置き換えれば、短期的な利益よりも「信頼されること」を優先する経営スタイルとも言えます。
部下や従業員の暮らしや心の安定を思いやることは、結果として組織の力を高める“戦略”なのです。
逆境を乗り越える組織文化の力
戦国時代の家臣たちは、常に生死をかけて戦う中で、上からの理不尽な命令に従わざるを得ない場面も多かったでしょう。
そんな時でも、氏康が家訓で示した「思いやり」や「公正さ」は、家臣たちの心理的な安心感につながっていました。
いま話題の「心理的安全性」という言葉がありますが、まさに氏康の家訓は、500年前にそれを実践していたようなもの。
人は安心できる環境でこそ、力を発揮し、組織全体が強くなるのです。
まとめ|現代ビジネスに活かす氏康の教え

戦国武将・北条氏康の家訓は、決して「古いお話」ではありません。
現代の私たちにも通じる、リーダーとしての本質的な価値観を教えてくれます。
- 礼節・公正を忘れない:競争社会でも、まずは相手を尊重する姿勢を持つ
- 私利私欲ではなく、大義に基づく判断を:組織のビジョンを共有し、メンバーの信頼を得る
- 民(メンバー)の安心を守る:部下や顧客の「心理的安全性」を大切にする
このような価値観は、時代を問わず、成果だけを追わない本当のリーダーシップを形づくります。
「らぼのすけ的家訓脳」で歴史を学び、行動のヒントに変える──。それが、ぼくたちがこの乱世(現代)を生き抜くうえでの武器になるのではないでしょうか。
次回は「北条氏康の外交術」について、彼の人間関係術を現代に置き換えて考えてみたいと思います!
それでは、また次の“戦国知恵袋”でお会いしましょう!