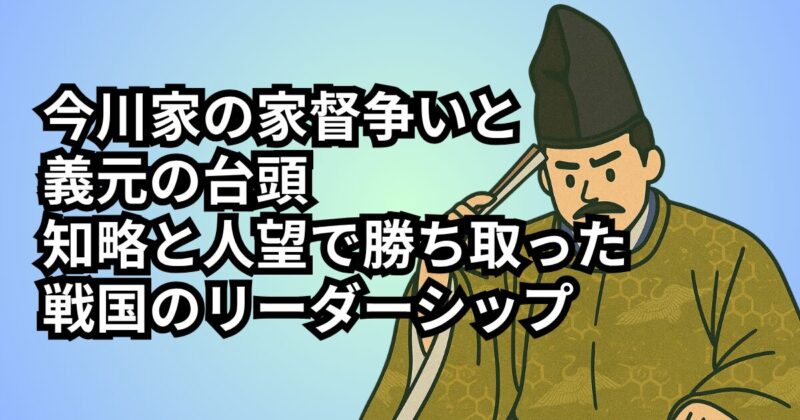はじめに|「負けた大名」ではない今川義元の真価
桶狭間の戦いで織田信長に敗れた――そんな印象が強い今川義元。しかし、彼の本当の凄さは「戦に負けた」ことではなく、それまでに築き上げた政治力・知略・人望にあります。
特に注目すべきは、若き義元が家督争いを乗り越えて当主の座に就いた過程です。単なる武力ではなく、情報戦や調整力、そして“根回し”を駆使して勝利を掴んだ義元の姿は、現代に通じる「リーダーシップ」のヒントに満ちています。

家督争いの背景|父・氏親の死と“戦国あるある”
今川家は、室町幕府の守護大名を出自とする由緒ある家柄。義元の父・今川氏親は駿河(静岡県中部)を中心に勢力を持つ実力者でしたが、彼の死後、**家督争い(かとくあらそい)**が起こります。
🧩 家督争いとは?
大名の家で、当主の死後に誰が後を継ぐかを巡って起きる争い。正妻の子か、側室の子か、はたまた兄か弟か……血筋や家臣の支持が重要になります。
義元には兄・今川氏輝(うじてる)がいましたが、彼は若くして急死。その後、氏輝に近い家臣たちは**異母兄の玄広恵探(げんこうえたん)**を推す一派を結成。一方、義元を支持する家臣団と真っ向から対立し、今川家は“内戦”状態に陥ります。
義元が選ばれた理由|文武を超えた“調整力”
このとき、義元はなんと「僧侶」でした。もともと出家しており、「栴岳承芳(せんがくしょうほう)」という法名を持っていた義元は、政治から距離を置いた存在と見られていたのです。
それでも義元は、あえて僧衣を脱いで還俗(げんぞく)。つまり、俗世に戻って当主争いに参戦します。
🧩 還俗とは?
僧侶や神職が俗世に戻ること。戦国時代では、出家した者が家督争いに加わるケースもありました。
この決断自体が、すでに彼の“勝負師”としてのセンスを物語っています。義元は、以下のような戦略的な行動を重ねて支持を固めていきました。
- 有力家臣に対する細やかな根回し
- 僧侶時代に築いた人脈の活用
- 敵対勢力との無用な争いを避けた交渉力
- 今川家の安定を第一とする“正当性”の訴求
これらの働きかけの末に、義元は「家のために必要なリーダー」として支持を集め、兄との争いに勝利します。
恵探の最期と、義元が得たもの
最終的に、恵探派との抗争は武力衝突となり、義元軍が勝利。恵探は敗走の末、自害する形で家督争いは終結します。
義元にとってこれは単なる勝利ではなく、**「戦を避ける努力をし尽くしたうえでのやむを得ぬ戦い」**でした。この姿勢こそが、のちの外交・内政における義元の特徴にもつながっていきます。
ここで義元が得たのは、単に“当主の座”だけではありません。家臣団の信頼、そして「争いを収める力」を見せたことで、“長期的な支配”の土台を築いたのです。
義元の初期統治|家中の安定と分国法の整備
義元が当主になったのちは、家中の対立が再発しないように入念な体制整備を進めました。最も重要なのが、**今川仮名目録(いまがわかなもくろく)**の整備です。
🧩 今川仮名目録とは?
今川家で用いられた分国法(家内法)のこと。家臣や領民に対する法制度を仮名でわかりやすく定めたもの。
この法令では、家臣の不正を禁じる条項や、民の財産を守る条文が明記されており、領国内に秩序と安心をもたらしました。
義元は、過去の家督争いでの痛みを糧に、**法と組織で“人が争わない仕組み”**をつくり上げようとしたのです。
なぜ義元は「敗者」とされるのか?
桶狭間の戦い(1560年)で織田信長に敗れたことにより、今川義元は長らく「油断した愚将」や「驕った大名」と語られがちでした。
しかし、それは一面にすぎません。今回紹介した家督争いの勝利や統治力、そして分国法の整備は、信長すら取り入れた先進的な制度の先駆けだったのです。
義元の本質は、「いかに戦わずして勝つか」「どうすれば秩序が続くか」に心を砕いた、極めて合理的で平和志向のリーダーだったのです。
現代ビジネスに活かす|らぼのすけ的・義元に学ぶリーダーの条件
ぼく「らぼのすけ」は、今川義元の家督争いを通じて、以下のようなリーダー論を学びました。
💡 1. 決断のタイミングを逃さない
義元が還俗したタイミングは絶妙でした。**「動かないことで機会を失うリスク」**を理解していたからこそ、勇気ある行動がとれたのです。
💡 2. 根回しと対話こそ最強の武器
義元の勝因は、武力ではなく人の心を掴む“説得力”。現代でも、調整力・根回し力・対話力がチーム運営の鍵です。
💡 3. 一度争った相手とも“再協力”できる体制づくり
敵対した家臣を追い詰めることなく処遇した義元。これは組織内の対立を引きずらない“心理的安全性”を生む行動であり、現代のマネジメントにも通じます。
おわりに|義元の「勝利」は桶狭間の前にあった
今川義元は「桶狭間の敗将」ではありません。それまでの彼の統治・調整・先見性を見れば、むしろ戦国屈指のリーダーであったことがよくわかります。
一度も血を流さずに家督を継げる人はいませんが、“どう争いを最小化するか”に知恵を尽くした人こそ、真に強いのではないか。義元の姿は、そう語りかけているように思えます。
次回は「今川家の内政改革と民政政策」にフォーカスし、義元が“住みよい国”をどうつくったのかを掘り下げていきます!
それではまた、次の“戦国知恵袋”でお会いしましょう!